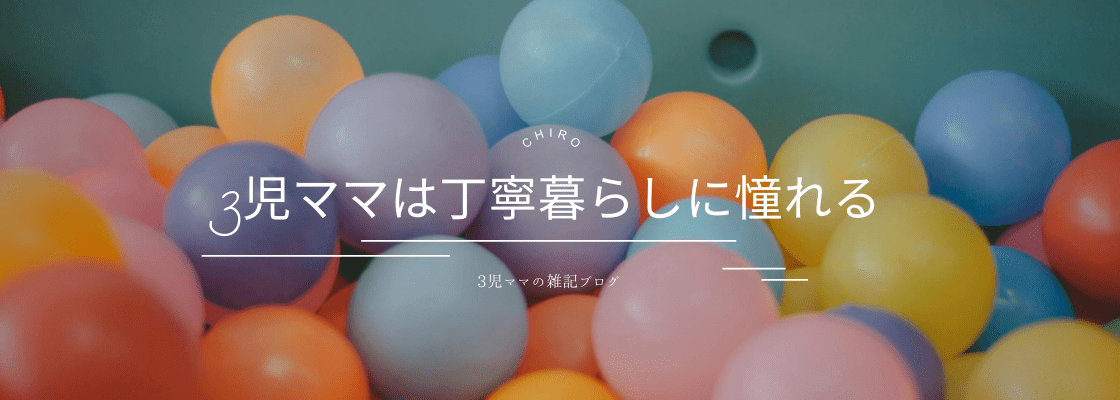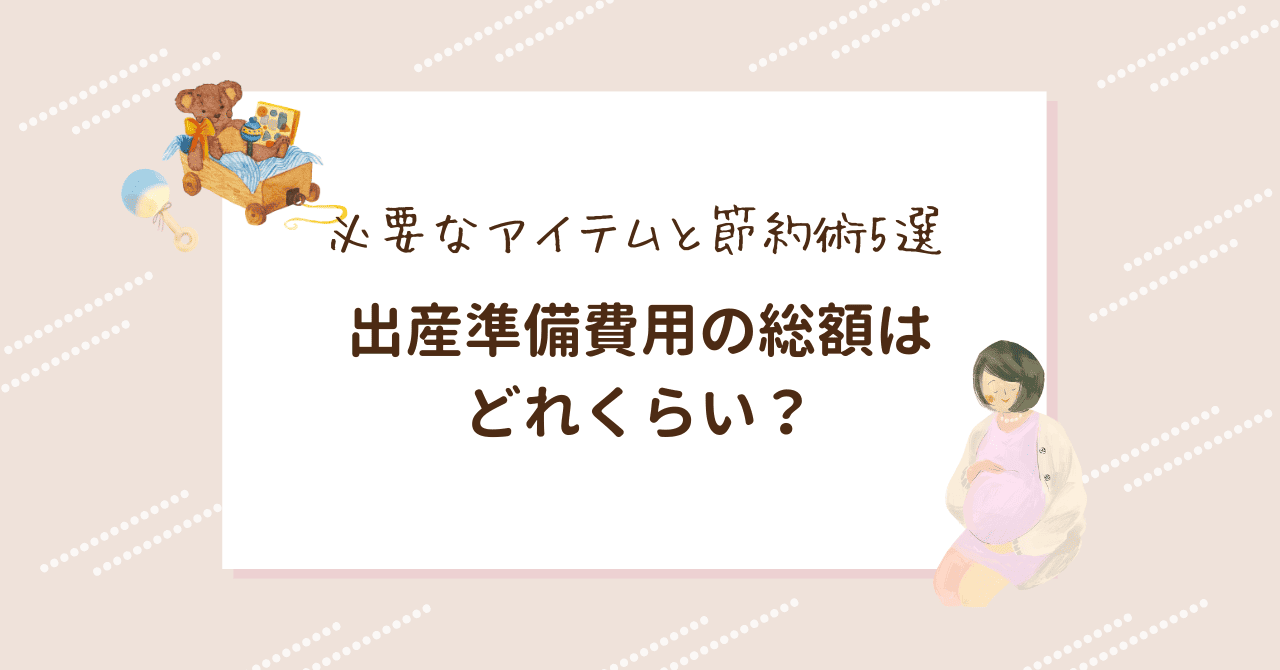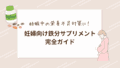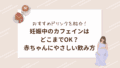赤ちゃんを迎える準備は、とても幸せな時間ですよね。
しかし、ベビー用品の準備や出産準備にかかる費用に、頭をかかえることも少なくありません。
今から出産準備をする人の中には、どのくらいのお金が必要なんだろう?と心配している人もいるでしょう。
この記事では、出産の際にかかる費用相場と節約ポイントを解説しています。
必要なアイテム一覧も紹介しているので、これから出産準備をする人は役立ててください♪
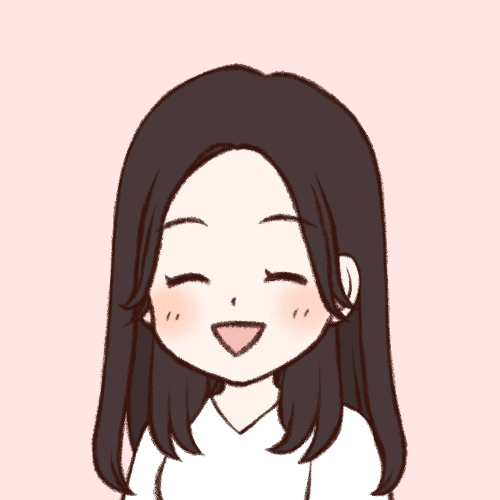
知らないと損する制度も紹介しているので、出産を控える人は要チェック!
出産準備費用の全国平均額はいくら?
出産にかかる費用は、大きく分けて3つあります。
すべての費用を合わせると、平均して70万円近くなるといわれており、計画的に準備を進めなくては家計を圧迫してしまう可能性が高いです。
まずは、何にどれくらいの費用が必要なのかをくわしく紹介していきます。
ベビー用品一式・マタニティ用品の準備にかかる費用
初めての出産に臨む人は、ベビー用品の費用感がわからないという人もいるでしょう。
一般的に、ベビー用品の準備にかかる費用相場は、10万円~15万円程度といわれています。
近年の物価高や選ぶアイテムによって、30万円以上かかることも珍しくありません。
下記に必要なものリストと金額の目安をリストアップするので、購入する際の参考にしてください。
| ベビー用品 | 費用目安 |
|---|---|
| ベビーカー | 5万~10万円 |
| ベビーベッド・寝具 | 1万~5万円 |
| チャイルドシート | 2万円~5万円 |
| ベビーバス | 2,000円~4,000円 |
| 抱っこ紐 | 1万円~2万5,000円 |
| 肌着(短肌着or長肌着5枚+コンビ肌着5枚) | 1万円 |
| 服(カバーオール5枚) | 1万円 |
| おむつ・おしりふき | 5,000円~1万円/1か月 |
| ミルク | 5,000円~1万円/1か月 |
| 衛星用品(ベビーソープ・保湿剤・綿棒・爪切り) | 3,000円 |
| 哺乳瓶・洗浄グッズ | 3,500円 |
マタニティアイテムにかかる費用の相場は、8万円程度です。
「入院時に使用するものを全部自分で用意しなくてはいけない」という場合は、その分費用も高くなります。
マタニティアイテムとして用意しておきたい最低限のリストを、下記にリストアップしているので参考にしてください。
| マタニティ用品 | 費用目安 |
|---|---|
| マタニティウェア | 2万円~4万円 |
| マタニティパジャマ | 6,000円 |
| 産褥ショーツ | 1,600円 |
| 産前・産後下着 | 1万円 |
| 母乳パッド | 1,000円/1か月 |
| 乳頭ケアクリーム | 1,500円 |
| 授乳クッション | 4,500円 |
| 母子手帳ケース | 3,000円 |
| 葉酸サプリ | 4,000円/1か月 |
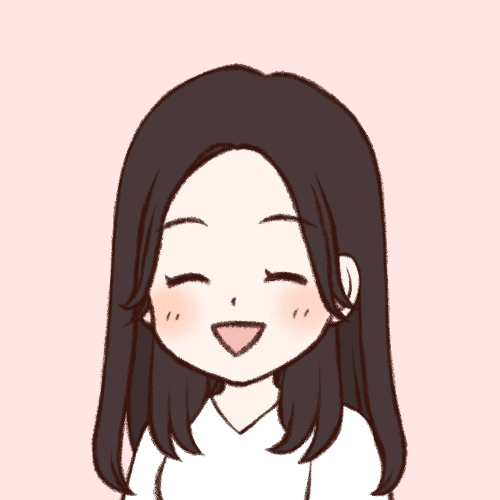
必要に応じて、骨盤ベルトやセレモニードレスの購入も検討してみてください!
妊婦検診の費用
妊娠中はトータル14回の検診があり、合計自己負担額は平均4万円~7万円程度といわれています。
妊娠中の定期健診は、保険が適用されないため、基本的に全額自己負担です。
自治体が一部費用の助成を行っているため、お住まいの自治体によって費用が大きく異なります。
ちなみに、仙台市では令和6年4月から助成費用が引き上げられました。
また、従来は14回目までの妊婦検診を対象に助成をおこなっていましたが、令和6年4月からは15回・16回目の検診も助成対象となっています。

令和6年秋に出産を予定していますが、自己負担額が500円以内に収まることが多いです♪
病院への交通費
妊娠中は定期的に病院へ通わなくてはいけないため、交通費が発生します。
領収書がある場合、交通費は通院費として確定申告可能です。
自己負担額を軽減したい場合は、公共交通機関やタクシーの利用を検討してみてください
出産にかかる費用
出産費用の相場は、30万円~70万円です。
自治体によって出産費用に大きく開きがあり、一番分娩にお金がかかるのは東京、次いで神奈川、栃木、宮城と続きます。
また、出産方法によっても自己負担額は異なります。
無痛分娩を選択すると、出産費用はより高額です。
逆に、自己負担額が少ないのは健康保険が適用される帝王切開です。
任意保険も適用されるので、帝王切開で出産する可能性がある人は、加入している保険会社に保険金の請求方法などを問い合わせておきましょう。
主な出産方法とその費用相場は、以下の通りです。
| 出産方法 | 費用相場 |
|---|---|
| 病院での自然分娩 | 46万円~50万円 |
| 病院での無痛分娩 | 66万円~70万円 |
| 病院での帝王切開 | 6円~7万円 |
| 助産院での自然分娩 | 48万円 |

出産する病院によっては、分娩予約時に20万円程度の予約金が必要なことも…。
出産内祝いの相場は?両親・親族・友人・会社それぞれの費用を紹介
出産後に、お祝いとして贈り物をもらうことも多いでしょう。
出産のお祝いを頂いたら、内祝いとしてお返しを送らなくてはいけません。
内祝いは、産後1週間~1か月以内に送るのが一般的といわれています。
費用は、いただいたお祝いの半分~1/3が相場です。
相手との関係性によっては、設定金額が失礼に当たる場合もあるので注意しなくてはいけません。
内祝いを送る際は、下記表を参考に金額を設定してみてください。
| 間柄 | 内祝いの相場 |
|---|---|
| 両親 | 1/2~1/3が相場 出産祝いが高額だった場合、1万円程度でお返しをする人が多い |
| 親戚 | 年配の方へは1/3、若い親戚には1/2が相場 家族間の慣習もあるため、お返しする前に両親へ相談するのがおすすめ |
| 友人 | 1/2が相場 |
| 会社関係 | 上司へは1/3、同僚や部下へは1/2が相場 連名でいただいた場合は、いただいたものの金額を人数で割り、その金額を目安に内祝いを用意しましょう |
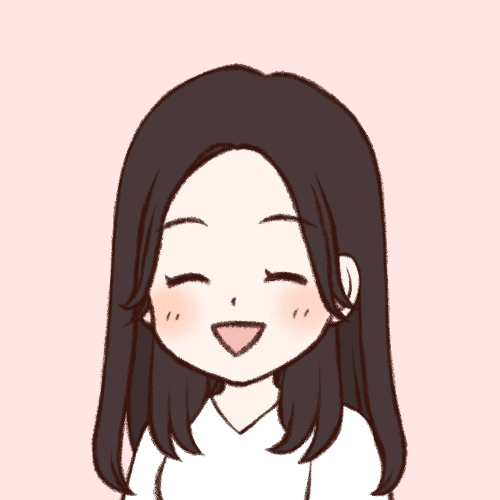
産後間もなくは体調が思わしくないママも多いので、パパが主体になって行動してくれるとうれしいですね!
出産準備費用の節約方法7選
出産には、さまざまな節約方法や補助金制度があります。
特に、地方自治体が実施している補助金や助成について、しっかりと調べておくことが大切です。
賢く利用して費用の負担を軽減しましょう!
補助金や助成を利用する
出産に関して利用できる補助金や助成は、大きくわけて4種類あります
妊娠・出産に関する助成制度
妊婦検診は基本的に自己負担ですが、自治体が一部助成を行っています。
母子手帳を受け取りにいくとき、一緒に妊婦検診の助成券がもらえるので、検診時に利用しましょう。
また、健康保険に加入している人は、出産時に出産一時金が支給されます。
子一人につき50万円が支給され、病院に直接支払われる方法を選ぶことで、自己負担額が軽減可能です。
さらに、通常分娩の場合保険診療外ため利用できませんが、帝王切開や異常分娩の場合は高額療養費制度が活用できます。
高額療養費制度は、1か月の保険診療の窓口金が自己負担額の上限を超えた際に、その差額を支給する制度です。
事前に加入している保険組合や国民保険から限度額適用認定証を取り寄せておくと、万が一の際スムーズに手続きが行えます。
妊娠・出産に関する優遇措置
妊娠・出産に関する優遇措置として、年金や健康保険の免除があります。
加入している年金や健康保険によって免除時期がことなるので、注意してください。
| 種類 | 免除期間 |
|---|---|
| 国民年金・国民健康保険 | 出産予定前月~4か月間 |
| 健康保険・厚生年金保険 | 出産予定日の6週間前から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで |
妊娠・出産に関する補助制度
妊娠・出産に関する補助制度には、出産・子育て応援交付金があります。
令和4年から始まったこの制度は、妊娠から出産、子育てを一貫して支援するための制度で、産前・産後に5万円ずつ、計10万円の給付が受けることが可能です。
また、自治体独自に妊娠や出産に関する補助を行っていることもあります。
例えば仙台市では、新生児誕生祝福事業として「杜っ子のびすくプレゼント」を行っていて、出産後に3万円分のカタログギフトを受け取れます。
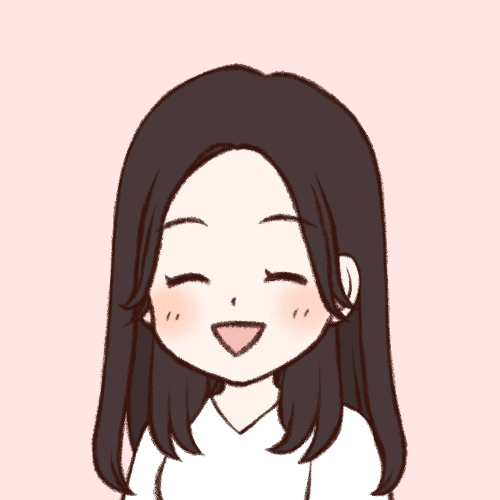
自分の住んでいる自治体での補助制度をチェックする場合、各市町村のHPをチェックしてみてください♪
妊娠・出産に関する給付金
妊娠・出産には喜びだけでなく、仕事や収入に関する不安もつきものですよね。
そんな不安をサポートするのが、国や企業の制度による「給付金」です。
ここでは、代表的な4つの給付制度についてわかりやすく解説します。
| 給付金名 | 対象者 | 支給期間 | 支給額の目安 | 申請先 |
|---|---|---|---|---|
| 出産手当金 | 健康保険加入の会社員・公務員など | 出産予定日の6週前〜出産後8週まで | 給与の約2/3(日給ベース) | 勤務先を通じて健康保険組合 |
| 育児休業給付金 | 雇用保険加入者 (男女問わず) | 原則:子どもが1歳になるまで | 開始6か月:給与の67%、以降は50% | ハローワーク (会社経由) |
| 出生時育児休業給付金 | 雇用保険加入の父親 | 出生後8週以内に最大4週間の休業 | 給与の約67% (一定要件あり) | ハローワーク (会社経由) |
| 出生後休業支援給付金 | 雇用保険加入者 (父母どちらでも可) | 最大28日間 (両親で育休取得が要件) | 賃金日額×日数×13% (育休給付と合わせて80%) | ハローワーク (会社経由) |
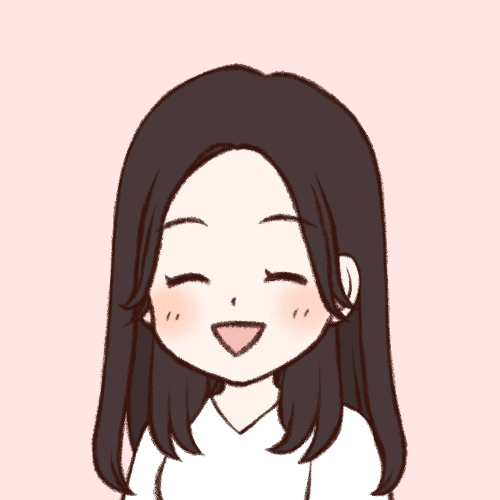
2025年に新設された「出生後休業支援給付金」のお陰で、お給料の手取り額相当の給付金が受給できるようになりました♪
医療保険の活用方法
妊娠中や出産って、何が起こるかわからないからこそ、できるだけ安心できる準備をしておきたいですよね。
じつは、加入している医療保険に「女性疾病特約」や「出産特約」がついていると、分娩時の入院費用や、帝王切開などの手術費がカバーされることがあるんです。
たとえば…
- 帝王切開での出産になった場合
- 妊娠高血圧症候群や切迫早産での長期入院
- 出産後のトラブルで再度入院が必要になった場合 など
このようなケースでは、入院給付金や手術給付金がもらえる可能性があります。
「自然分娩は対象外じゃないの?」と思う方もいるかもしれませんが、合併症や医療処置がともなうと保険の対象になることもあるので、一度、今の保険内容を確認してみるのがおすすめです。
とくに、妊娠前から加入している医療保険なら、ほとんどのケースで給付対象になる可能性が高いです。逆に、妊娠がわかってから加入した保険には、保障されない「待機期間」がある場合もあるので、注意が必要です。
「うちは大丈夫かな…?」と不安な方は、保険会社や担当者さんに聞いてみると安心ですよ。
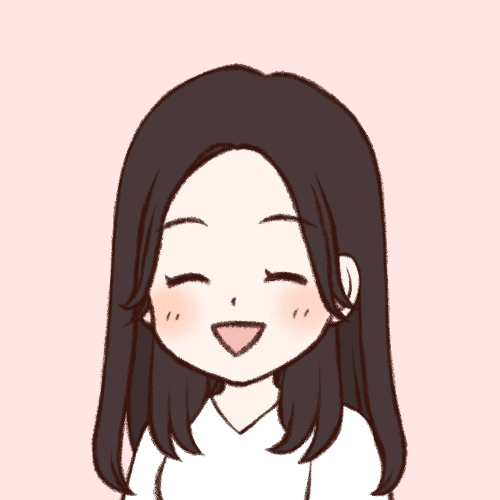
医療保険も、出産準備のひとつとして見直してみてくださいね。
ベビー用品の節約方法
赤ちゃんを迎える準備って、楽しみな反面、「いったい全部でいくらかかるの?」と心配になりますよね。
でも実は、リサイクルやレンタルをうまく活用すれば、ベビー用品一式の費用をグッと抑えることができるんです。
平均で10〜20万円ほどかかると言われるベビー用品ですが、工夫しだいでその半額以下にすることも可能です。
リサイクル利用法
赤ちゃんのアイテムって、使う時期がとっても短いんですよね。だからこそ、状態のよい中古品を上手に選べば、新品にこだわらなくても十分。
- リサイクルショップや子ども用品の専門店
- メルカリやラクマなどのフリマアプリ
- 地域の掲示板やママ同士のコミュニティ
こういったところで探すと、意外とキレイでお手頃なものが見つかります。
とくに、ベビーベッドやバウンサー、洋服類はリサイクル品でも満足できるケースが多いですよ。
「お下がり」の活用法
身近に育児経験者がいるなら、「お下がりを譲ってもらう」ことも大きな節約になります。
受け取る前に、ほしいもの・不要なものをあらかじめリストアップしておくと、ムダなく、使えるものだけをもらえるのでスッキリしますよ。
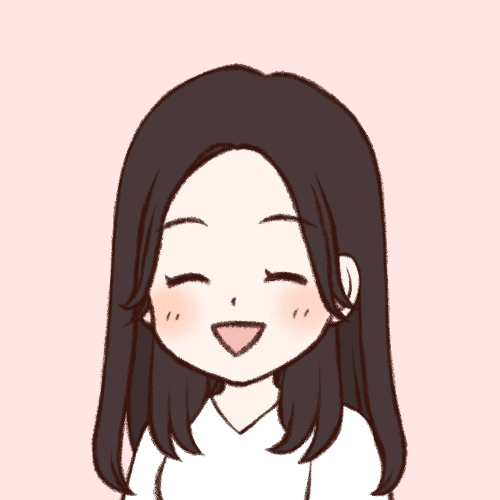
ベビー服、おもちゃ、哺乳瓶、抱っこ紐など、短期間で使わなくなるものは特におすすめです。
セール・クーポン情報
欲しいアイテムがある程度決まったら、セールの時期をチェックしておきましょう。
- 出産準備品が安くなる「年末年始」「新生活セール」「ベビー&マタニティフェア」
- 楽天スーパーセールやAmazonタイムセール
- ベビー用品店のアプリクーポンやポイント還元
こういったタイミングを活用するだけでも、出費をかなり抑えることができます。
まとめ買いの予定がある方は、事前にリストを作っておくのがおすすめです。
出産準備費用の計画を立てよう!具体的な予算の組み方
赤ちゃんを迎えるのが楽しみな一方で、気になるのが「お金」のこと。
あれもこれもと買っていたら、いつの間にか予算オーバー…なんてこともありますよね。
そんな事態を防ぐには、早めにざっくりとした予算を立てておくことがポイントです!
「全部そろえる」のではなく、「何が必要かを見える化する」ことで、ムダを防げて安心感もぐっと増しますよ。
出産準備費用を計画的に管理する
いきなり買い物に走る前に、まずは3ステップで予算計画を立ててみましょう。
- 必要なアイテムをリストアップ
- それぞれの価格をざっくり調査
- 優先順位をつけて予算を割り振る
まずは、ベビーベッドやベビーカー、肌着、おむつ用品など、思いつく限り必要なものを一度全部書き出してみましょう。
その後、新品・中古・レンタルの価格を比較して、どの方法が自分に合っているかも見極めます。
さらに、「今すぐ必要なもの」「出産後でもOKなもの」に分けて、購入時期をずらしておけば、一度に大きな金額を動かすのを避けられます。
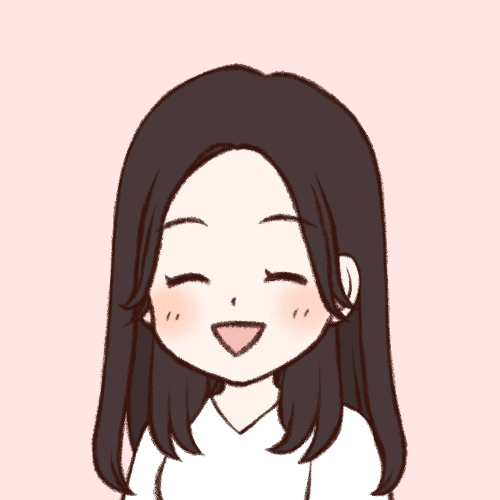
「いくらかかるのか」「今なにをすべきか」がハッキリして、気持ちにも余裕ができますよ。
出産準備費用の月ごとの予算配分のポイント
出産準備品を一気に買い揃えると、どうしても家計に負担が…。
だからこそ、月ごとに少しずつそろえていくのがコツです。
たとえば、妊娠初期〜中期は、ベビーベッドやチャイルドシートなどの大物アイテムを準備します。
レンタルや中古も視野に入れて検討すると、出産準備費用を抑えられます。
妊娠後期には、消耗品やこまごましたものを購入しましょう。
肌着やおむつ、ガーゼ、哺乳瓶など、使用頻度が高くてすぐに必要になるものを中心に揃えるのがおすすめです。
このように月単位で分けて考えることで、急な出費を防ぎつつ、出産直前にも慌てずに済みます。
さらに、ボーナス時期やセールのタイミングに合わせて、計画的に買い物できるとよりおトクに準備ができますよ。
出産準備費用のよくある質問
出産準備を始めると、「これってどうするの?」「お金、大丈夫かな…」と不安になることもありますよね。
ここでは、ママたちからよく寄せられるお金に関する質問に、わかりやすくお答えしていきます。
出産準備費用の払い戻しや補助金はあるの?
出産にかかる費用の一部は、国の制度や自治体のサポートによって軽減できるんです。
代表的なのが「出産育児一時金」で、健康保険に入っていれば原則50万円が支給されます。
この制度を利用すれば、出産費用の大部分をカバーできます。
また、妊婦健診や通院・分娩費用などが一定額を超えると「医療費控除」の対象になる場合もあります。
確定申告をすることで、支払った医療費の一部が戻ってくる可能性があります。
自治体によっては、ベビー用品購入への補助や育児サポートの制度があるところも。
まずはお住まいの自治体や保険会社の窓口をチェックしてみましょう。
お金がない!出産準備費用が足りない場合の対策方法
もし予算が足りないと感じたら、まずは「今すぐ必要なもの」から優先的にそろえていきましょう。
退院時の服やおむつ類など、最低限で大丈夫です。
ベビーベッドやバウンサーなどは、使用期間が短いため、中古やレンタルでも十分です。
フリマアプリやリサイクルショップ、知人からのお下がりなどを活用すると、大幅な節約につながります。
また、補助金や給付制度を積極的に利用することで、出費を抑えることができます。
すべてを一度にそろえる必要はないので、無理のないペースで準備していきましょう。
不安を減らして楽しく出産準備を進めよう
出産準備には多くの費用がかかりますが、補助金や給付金、リサイクル・レンタルの活用で負担を軽くすることができます。すべてを一度にそろえる必要はなく、必要なものをリストアップし、優先順位を決めて計画的に準備することが大切です。
国や自治体の制度も活用しながら、自分に合った方法で、安心して赤ちゃんを迎える準備を進めていきましょう。